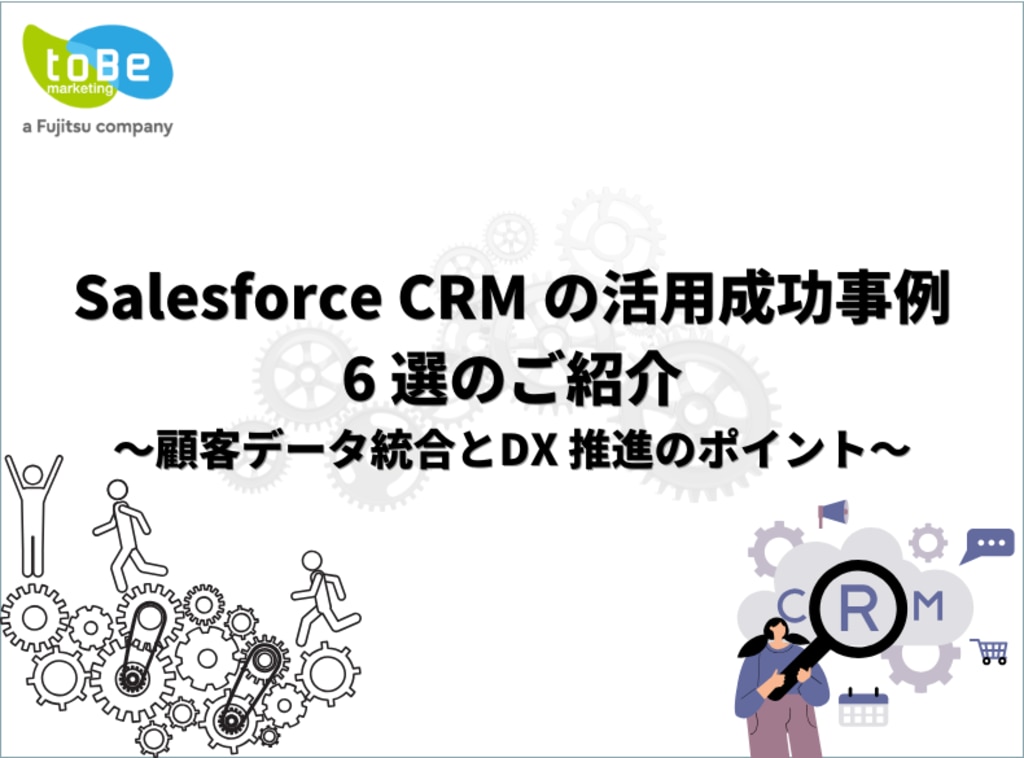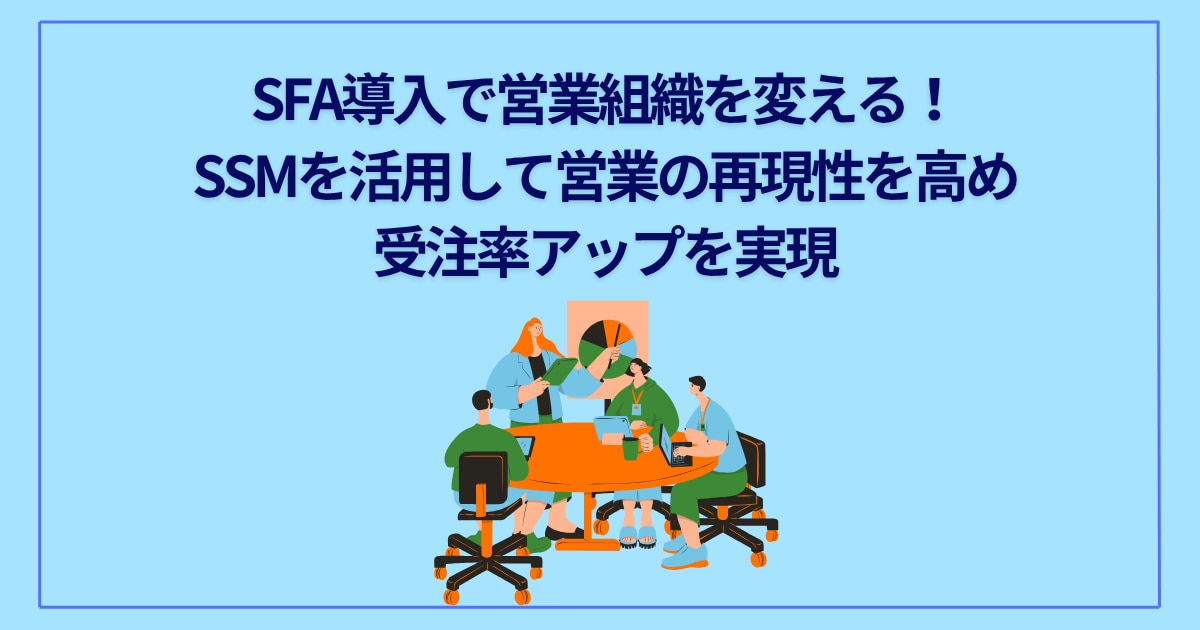
SFA導入で営業組織を変える!SSMを活用して営業の再現性を高め、受注率アップを実現
Salesforce CRMの活用成功事例 6選のご紹介 〜顧客データ統合とDX推進のポイント〜
本資料は、Salesforce CRMを活用した顧客データの統合および業務プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX )に取り組む企業様の成功事例を多数ご紹介しております。
\詳細はこちらをクリック/
はじめに:SFAを入れても成果が出ない?
いまや多くの企業が営業支援システム(SFA)を導入しています。
しかし、現場からはこんな声を耳にすることも多いのではないでしょうか。
「入力が面倒で使われていない」
「データがバラバラで結局Excel管理に戻っている」
「SFAを入れても売上が変わらない」
SFAの導入目的は、本来「営業の生産性向上」や「属人化の解消」などにあります。
ところが、実際には“営業活動そのものが整理されていない状態”でツールを導入してしまい、現場が混乱するケースが後を絶ちません。
そのような課題を解決するための考え方として、近年注目されているのが
「セリング サクセス メソドロジー(Selling Success Methodology:SSM)」です。
この記事では、SFA導入を成功に導くためのステップとともに、SSMを軸にした営業活動の可視化・定着化の方法を詳しく解説します。
toBeマーケティング株式会社では、Salesforceの導入から活用、運用支援までを幅広くサポートし、お客様のビジネス成長に貢献いたします。
Sales Cloudの初期構築はもちろん、Account Engagement(旧Pardot)をはじめとする他のSalesforce製品との連携を見据えた最適なチューニングも可能です。
⇒ Salesforce導入支援の詳細はこちら
さらに、顧客情報基盤の構築や営業活動の効率化、マーケティングとの連携強化を通じて、データに基づいた意思決定を実現できる体制づくりをサポートします。
⇒ 詳細はこちらよりお気軽にお問い合わせください!
SFAとは?いま改めて注目される理由

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を自動化・可視化するための仕組みです。
商談や顧客情報、アプローチ履歴などを一元管理することで、営業活動の属人化を防ぎ、データに基づいた営業判断を可能にします。
かつては「営業のための管理ツール」という印象が強かったSFAですが、近年では営業DX・働き方改革・リモート営業の定着などにより、再び注目が高まっています。
SFAとCRMの違い
CRM(顧客関係管理):顧客満足度向上やロイヤルティ醸成が目的
SFA(営業支援システム):売上拡大・商談管理・営業効率化が目的
つまり、CRMが「顧客との関係構築」を重視するのに対し、SFAは「営業活動の可視化・生産性向上」を重視します。
多くのSFA導入が失敗する理由
SFA導入の失敗原因の多くは、“営業プロセスが明確でないままツールを入れてしまう”ことです。
たとえば、
商談フェーズの定義が曖昧
営業担当ごとにヒアリング内容がバラバラ
成功要因が分析できない
これでは、いくら高機能なツールを導入しても効果は出ません。
なぜなら、SFAは「正しい営業活動の構造」があってこそ力を発揮するものだからです。
ここで重要になるのが、次に紹介する「セリング サクセス メソドロジー(SSM)」の考え方です。
SSM(セリング サクセス メソドロジー)とは?

SSMとは、トップ営業の成功要因を分析し、“営業活動を再現可能なプロセス”に体系化するメソドロジーです。
営業という仕事は属人化しやすく、「感覚」や「経験」に依存しがちです。しかしSSMは、それを科学的に整理します。
SSMの特徴
成功営業の行動・質問・判断を明文化
商談のどのタイミングで何を確認すべきかを可視化
成果を出すための“営業設計図”をつくる
SFAを導入する前にSSMを設計することで、「何を入力するのか」「どんな情報を可視化すべきか」が明確になり、
営業活動そのものが標準化・再現化されます。
SSMをベースに営業活動を整理・可視化する方法
ここでは、SSMを活用して営業活動を構造化し、SalesforceなどのSFA上で運用する具体的なステップを解説します。
Step1:現状把握とトップ営業の行動抽出
まずは、トップ営業がどんな活動をしているかを洗い出します。
どんな質問をしているか
どんな情報を引き出しているか
どんなタイミングで提案しているか
成功商談・失注商談を比較し、「成果に直結する行動・情報項目」を特定します。
Step2:SSMチェックリスト化
抽出した要素をもとに、営業活動のチェックリストを作成します。
代表的な項目は以下のようなものです。
意思決定者の特定
顧客の課題・目的の明確化
導入理由と期待効果
競合の存在
導入タイミング・予算確定時期
これらを定量的にスコア化することで、商談の健全性を“見える化”できます。
最初は5項目程度から始め、運用に慣れてきたら項目を増やすのがおすすめです。
Step3:Salesforceでの実装
SSMをSalesforceに組み込むことで、日々の商談活動をデータ化できます。
商談オブジェクトにSSM項目を追加
PathやFlowでフェーズごとに必須項目を設定
ダッシュボードでチーム別SSMスコアを可視化
たとえば、「SSMスコア70点以上の商談は受注率45%」「50点以下は15%」など、営業精度を数値で把握できます。
Step4:組織全体への展開
可視化したデータを活用し、営業会議や1on1で議論することで、ノウハウ共有が進みます。
「SSMチェック項目の抜けが失注要因だった」など、改善のサイクルを回せるようになります。
SFA導入プロジェクトを成功させるステップ

SFAを定着させるには、「ツール導入」ではなく「営業文化の変革」が必要です。
以下の5つのステップで進めると、定着率が格段に上がります。
Step1:目的設定と成功指標の明確化
まずはプロジェクトのゴールを具体的に定義します。
定量、定積的なゴールを作ることを意識すると、導入の優先項目やSFAの設定内容をブレずに決められます。
定量目標
受注率を〇%向上
商談期間を△日短縮
入力率100%を目指す
定性目標
トップ営業のナレッジを組織で再現可能にする
商談活動の属人化を解消
マネージャーによる営業指導が効率化される
Step2:現状分析とSSM仮設設計
現場の営業活動を洗い出し、SSM(セリング サクセス メソドロジー)をベースにチェックリストを作成します。
例えば、下記のようなものをチェックリストにできるとよいでしょう。
商談履歴・失注理由・成功事例を分析
トップ営業へのヒアリングで成功行動を抽出
「必ず確認すべき項目」を5〜14項目に整理
例:意思決定者、課題・導入理由、競合情報、導入タイミング、ROI期待値など
成果物例:
ExcelまたはGoogleスプレッドシートにSSMチェックリストを作成
商談ごとのSSMスコアリング表
Step3:Salesforceでの具体的構築
SSMを基盤に、Salesforce上で再現可能な仕組みを作ります。
いきなり完璧なものを作る必要はありません。メンバー全員が取り組みやすいよう、初期段階では「入力しやすさ」を重視し、チェック項目は最小限からスタートすることをお勧めします。
下記のような項目や設定、ダッシュボードの作成をすることで、定着化につながる可能性が高くなります。
商談オブジェクトにSSM項目を追加(Picklist・Number・Dateなど)
Path機能でフェーズごとの必須入力項目を設定
Flowを活用し、入力漏れや期日遅延を自動通知
ダッシュボード作成例:
チーム別SSM完了率
商談フェーズ別の未入力件数
SSMスコア別受注率
Step4:トレーニングと現場巻き込み
SFAの導入フェーズでは、システム構築だけでなく、現場の定着が最重要です。
現場参加型で進めるほど、メンバー全員の当事者意識が強くなり、導入初期の抵抗感は低くなります。
下記のような工夫をすることで、現場が一緒に取り組める環境をつくりましょう。
ロールプレイ・商談シミュレーションでSSMの理解を深める
入力作業のメリットを体感できるようにダッシュボードや通知を活用
チャンピオン制度:現場から模範ユーザーを選び、他メンバーのフォローや入力サポートを担当させる
Step5:KPI測定と改善サイクル
導入できたら終わりではなく、その後も改善を続けるために、定量・定性両面でモニタリングする必要があります。
モニタリングの結果をしっかりと分析し、より自社に合ったSFAの活用方法に取り組むことが重要です。
モニタリングはこのようなものが挙げられます。
SSMスコア別の受注率・商談期間を定期的にレビュー
入力率が低い場合は、原因(入力負荷・理解不足)を分析
チームごとのベストプラクティスを共有し、チェックリストを改善
成果物例:
月次レポート:SSMスコアと受注率の相関分析
商談改善アクションリスト
Step6:全社展開の計画
最後に、小規模チームでPOC(パイロット運用)を実施し、効果が確認できたら部門横展開へ進めます。
ここも一気に進めるのではなく、下記のようなフェーズで徐々に浸透させていきましょう。
フェーズ0:POC(3〜5名・10件商談)
フェーズ1:部門展開(営業全員)
フェーズ2:他部門との連携(マーケティング・カスタマーサクセス)
フェーズ3:継続改善(SSM項目追加やダッシュボード改善)
このStep1~Step6のように丁寧に導入~定着化に向けて進めることで、SFA活用を最大限できるようになります。
SSMの考え方を活かしたSFA活用事例
ここまで、考え方や活用ステップをご紹介してきましたが、実際にSSM(セリング サクセス メソドロジー)の考え方を活かしてSFAを活用している事例を3つご紹介します。
事例1:BtoB製造業/新規開拓営業の受注率向上
課題
新規開拓営業チームでは、商談が属人化しており、トップ営業しか受注できない状況でした。
また、商談情報が各営業の頭の中にあり、マネージャーも進捗やリスクを把握できず、平均受注率はわずか15%と低迷していました。
SSM活用・SFA設計
トップ営業の成功行動を分析し、「必ず確認すべき商談項目」をSSMチェックリストとして定義しました。
主な項目は以下の通りです。
意思決定者の特定
導入課題・期待効果
競合状況
ROI・導入スケジュール
これらをSalesforce商談オブジェクトに追加し、Path機能でフェーズごとの必須入力項目を設定。
さらに、ダッシュボードでSSMスコアを可視化することで、マネージャーが進捗やリスクをリアルタイムで把握できるようにしました。その結果、入力率、平均受注率の向上と、トップ営業のナレッジがチーム全体で再現可能になり、商談の属人化を解消することができました。
事例2:ITサービス企業/既存顧客向けアップセルの効率化
課題
既存顧客へのアップセル営業では担当者ごとにアプローチ方法が異なり、顧客情報や過去の商談履歴が散在していました。
その結果、次に打つべきアクションが不明確で、受注機会を逃すケースが多発していました。
SSM活用・SFA設計
SSMの考え方を使い、顧客接点の最適なタイミングと確認事項を整理しました。
現状利用状況の確認
顧客課題の変化チェック
導入効果やROIの再確認
これをSalesforceに反映し、インサイドセールス向けに自動リマインダーを設定。
さらに、ダッシュボードで「次にアプローチすべき顧客」と「SSM完了率」を可視化しました。
その結果、営業活動の標準化で効率が向上し成約率が向上。また、提案品質の均一化とチーム全体でのナレッジ共有が可能になりました。
事例3:BtoC金融サービス/インサイドセールスの商談予測精度向上
課題
電話やWeb商談を中心とするインサイドセールスチームでは、商談フェーズの定義が曖昧で受注予測が正確に立てられず、マネージャーも個別商談の状況を把握できませんでした。
SSM活用・SFA設計
商談進捗を数値化できるチェック項目をSSMで整理し、Salesforceで商談スコアを自動計算する仕組みを構築しました。
主な項目は以下です。
顧客の意思決定者確認
興味度・課題認識レベル
競合状況
商談リスクの有無
スコアをもとに「受注見込みが高い順」に商談リストを表示。
これにより、優先度の高い商談に集中して対応できるようになりました。
その結果、商談予測精度が向上し、リスク商談を早期に発見し、事前に対策を打てるようになりました。また、チーム全体の受注率を向上させることができました。
SFA導入・SSM活用に関するよくある疑問
SFA導入やSSMの設計を検討される際、企業からよくいただく質問の中に共通するテーマがあります。
ここでは、その代表的な疑問を整理しながら解説します。
まず多く寄せられるのが、「SSMはすべての営業組織に適用できるのか?」という点です。
結論から言えば、業種や営業スタイルを問わず活用可能です。
新規開拓型の営業であれば顧客情報の深堀りに、ルート営業であれば関係深化の可視化に、インサイドセールスであれば顧客温度感の判定に活用できます。
つまり、どんな営業モデルでも“成果に直結する活動”を明確化できるのがSSMの強みです。
次に多いのが、「現場がSFAに入力しなくなるのでは?」という懸念です。
確かに、入力作業が目的化すると現場の負担になります。
しかしSSMを導入し、入力した情報が“自分の成果に返ってくる”仕組みを設計すれば、この課題は解消されます。
Salesforceのダッシュボード上で、自分の商談スコアや成功パターンをリアルタイムに確認できるようにすることで、
「入力=自己成長」と感じられる運用を実現できます。
また、「中小企業にも必要なのか?」という声も多く聞かれます。
むしろ属人化が起きやすい中小企業こそ、SSM導入の効果が大きいと言えます。
個々の営業ノウハウを形式知として整理し、Salesforceに蓄積することで、
人が入れ替わっても営業力が下がらない“強い組織”を作ることができます。
最後に、SSMを導入する際の推奨ステップについて。
いきなりすべての項目を定義する必要はありません。
最初は「受注に最も影響する5項目」から始め、運用を通じて少しずつ拡張していくのが定着のコツです。
段階的に取り入れることで、現場への負荷を抑えつつ、確実に成果を出せます。
【toBeマーケティングの視点】SFA×MA連携が営業を劇的に変える
SFA単体でも効果はありますが、マーケティングと営業を分断させないことが、今のB2Bビジネスで勝つための定石です。
MA連携で実現する「攻め」の営業
toBeマーケティングが強みとする「Salesforce(SFA/CRM)× Account Engagement(旧Pardot/MA)」の連携により、以下のような成果が期待できます。
ホットリードの即時通知: 顧客がWebサイトの価格ページを見た瞬間に、営業へ通知を送る。
商談の優先順位付け: スコアリング機能により、成約確度の高い顧客に絞ってアプローチできる。
リサイクル(掘り起こし)の自動化: SFAで失注した案件をMAに戻し、適切なタイミングで再育成する。
toBeマーケティングの強み: 弊社はこれまで数多くのSalesforce導入・活用を支援してきました。単なるツールの設定ではなく、貴社の「マーケティングから営業までの全体設計」を伴走型でサポートします。
まとめ:SFA導入を「営業変革の起点」に
SFA導入の目的は、ツールを入れることではなく、営業活動を標準化し、再現性のある営業組織を作ることです。
その鍵を握るのが「セリング サクセス メソドロジー(SSM)」です。
SSMを基盤に営業プロセスを可視化し、Salesforce上で運用することで、データが“使える情報”に変わり、
組織全体の営業力が飛躍的に高まります。
SFA導入の成功は、「ツール導入」ではなく「営業の仕組み化」から始まります。
セリング サクセス メソドロジーを活用し、Salesforceで再現性のある営業組織を作りましょう。
それが、“使われるSFA”から“成果を出すSFA”へ変える第一歩です。
toBeマーケティングではSalesforce導入から活用支援まで幅広くサポート。営業組織全体の成果向上を目指す企業は、ぜひご相談ください。
Salesforce
使いこなせていますか?
事例から学ぶSalesforce活用法
本資料では、以下のような内容を通じて、CRMとMAを活用したマーケティング術を支援します。「なんとなく導入」ではなく、確実に成果へとつなげるためのヒントが詰まった1冊です。
\詳細はこちらをクリック/