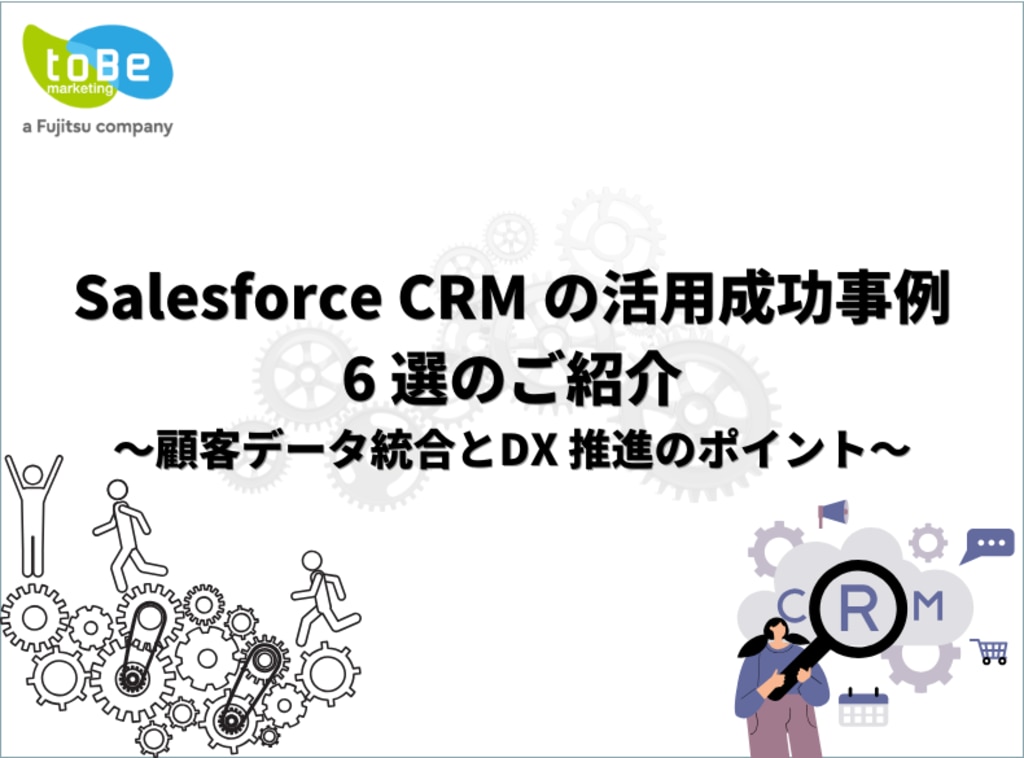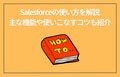Salesforceのデータ連携|ツール選定から運用まで徹底解説
Salesforce CRMの活用成功事例 6選のご紹介 〜顧客データ統合とDX推進のポイント〜
本資料は、Salesforce CRMを活用した顧客データの統合および業務プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX )に取り組む企業様の成功事例を多数ご紹介しております。
\詳細はこちらをクリック/
Salesforceと外部データやツールとを連携すれば、マーケティングや営業の業務効率を飛躍的に向上させることができます。しかし、効果的な連携を行うには、ツール選定やセキュリティー上の課題などに注意が必要です。
今回は、salesforce連携のメリット、連携すべきツールやデータ、最適な連携方法について見ていきましょう。
toBeマーケティング株式会社では、Salesforceの導入から活用、運用支援までを幅広くサポートし、
お客様のビジネス成長に貢献いたします。
Sales Cloudの初期構築はもちろん、Account Engagement(旧Pardot)をはじめとする
他のSalesforce製品との連携を見据えた最適なチューニングも可能です。
⇒ Salesforce導入支援の詳細はこちら
さらに、顧客情報基盤の構築や営業活動の効率化、マーケティングとの連携強化を通じて、
データに基づいた意思決定を実現できる体制づくりをサポートします。
⇒ 詳細はこちらよりお気軽にお問い合わせください!
salesforce連携のメリット

salesforce連携には、「共通の情報をもとに迅速な意思決定ができる」、また「顧客対応品質や営業効率が上がる」など、いくつかのメリットがあります。
更に、Account EngagementやMarketing Cloud EngagementなどのMAツールやサポートツールで集約した顧客行動データと連携すれば、顧客のフォローアップと営業効率向上にも役立つでしょう。salesforce連携のメリットについて、詳しく見ていきましょう。
1. 業務効率の向上
salesforceと外部データやツールを連携させると、連携データ入力の手間が削減され、部門間の情報共有もスムーズに行えます。
例えば、営業が案件情報をSalesforceに登録し、マーケティングチームはそのデータを元にキャンペーンを最適化するような連携をすれば、カスタマーサポートは、スムーズな契約更新の案内や追加サービスの提案ができるでしょう。手動でのデータ更新や重複入力の負担が減り、業務の効率化も期待できます。
2. 意思決定の迅速化
データ連携をしておけば、リアルタイムでデータを可視化できるため、スピーディーな意思決定にも繋がります。
例えば、tableauなどのBIツールとSalesforceを連携すると、売上推移やリード獲得状況を可視化でき、次の戦略を迅速に立案できるようになります。営業部門でも、ダッシュボードを活用して商談進捗をモニタリングすれば、適切なフォローアップのタイミングを見極めることができるでしょう。
3. 顧客エンゲージメントの強化
キャンペーン反応データやユーザー行動データをSalesforceに統合すれば、より精度の高いアプローチができます。
例えば、メール開封履歴やWebサイトの閲覧履歴を活用し、関心の高い見込み客にパーソナライズされたアプローチを行うことで、コンバージョン率向上も狙えます。
salesforceとの連携で飛躍的に効率化できるツールやデータ
salesforceと連携すべき代表的なデータに、「顧客の行動履歴」があります。また、Webサイトの閲覧履歴、メールの開封履歴、キャンペーン参加状況などをsalesforceと連携すれば、最適なタイミングで顧客にアプローチできるでしょう。
「営業関連データの連携」も重要です。商談履歴などをsalesforceに連携すれば、部署間の情報共有がスムーズになり、業務の重複やミスを防げます。
業務効率化のためには、MAツールやBIツールとの連携も効果的です。MAツールを上手く連携させることができれば、リード育成の自動化やスコアリングが可能になり、営業とマーケティングの連携も強化されるでしょう。
更に、BIツールと連携すれば、進捗状況をリアルタイムで分析し、迅速な意思決定ができます。
Salesforceと外部システムの連携方法

Salesforceが持つ機能を最大限生かすには、外部システムとのデータ連携が求められる場面が多くあります。では、実際にSalesforceと外部システムをどのように連携すればよいのか、具体的な方法を見ていきましょう。
1.データローダーを活用する
データローターは、Salesforceが提供するデータのインポート・エクスポートツールです。CSVファイルを介してデータを一括処理でき、特別なプログラミングスキルを必要としません。
このツールの利点は、導入が容易であり、一度設定すればデータの移行や管理が簡単に行えることです。開発コストを抑えつつ、短期間でデータの登録・更新ができるため、特に大規模なシステム開発が不要な環境で有効です。
一方で、リアルタイムでのデータ同期が難しく、連携のたびにCSVファイルを作成する手間が発生します。また、データの不整合が発生した場合には手動で対応する必要があるため、頻繁にデータの連携が必要な場合や、データの即時反映を求める場面には不向きでしょう。
2.データインポートウィザードを利用する
データインポートウィザードは、Salesforceに標準搭載されているデータ取り込みツールです。画面上のガイドに沿って操作を進められるため、プログラミング知識がなくても簡単にデータのインポートを行えます。
利用方法はシンプルで、CSVファイルをアップロードし、Salesforceの項目とデータの対応付け(マッピング)を行うだけです。Salesforce上から直接起動でき、専用ソフトのインストールも不要なため、初めてSalesforceを扱うユーザーでも扱いやすいツールといえるでしょう。
ただし、扱えるデータ量に上限があり、一度にインポートできるのは最大で5万件までです。また、すべてのオブジェクトに対応しているわけではなく、更新や削除などの高度なデータ操作にも制限があります。そのため、より複雑なデータ処理や定期的なバッチ処理には、データローターやAPI連携の導入を検討した方がよいでしょう。
3. Web APIを利用する
APIは、システム間でデータをやり取りするためのインターフェースです。Salesforceでは、SOAP APIやREST APIなど複数のAPIを提供しており、外部システムと直接通信を行うことでリアルタイムのデータ連携が可能になります。
この方法の最大の強みは、柔軟なカスタマイズ性です。SalesforceのAPIを利用すれば、企業の要件に合わせてシステム間のデータのやり取りを最適化できるため、業務プロセスにフィットした仕組みを構築できます。
しかし、API利用にはプログラミングスキルが求められ、属人化が進むとシステムの維持管理が困難になる点については注意しましょう。
4. データ連携ツール(EAI/ETL)を使用する
EAIやETLは、異なるシステム間のデータ連携を支援するツールです。Salesforceと外部システムのデータを自動で変換・転送し、スムーズな統合を実現します。
この方法なら、プログラミングの知識が不要で、直感的な操作でデータのやり取りができます。特に大容量データの高速処理に適しており、データの変換や出力先の振り分けを簡単に設定できる点も大きなメリットです。
ただし、EAI/ETLツールの導入にはコストが発生します。初期費用だけでなく、月額の利用料や運用コストが発生する点には注意しましょう。また、ツールの設定や運用にはある程度の知識が求められるため、スキルを持つ人材の確保も重要なポイントです。
5. データ連携クラウドサービス(iPaaS)を利用する
iPaaSは、クラウド上で複数のアプリケーションを統合するためのプラットフォームです。iPaaSは、ローコードまたはノーコードで開発できるため、高度な専門知識がなくても連携フローを構築できる点が特徴です。
iPaaSを利用するためには、連携先のシステムがAPIを提供していることが前提となります。そのため、APIを持たないシステムの場合は連携が難しいでしょう。
また、iPaaSにはさまざまな種類があるため、用途に応じた適切なサービスを選定することが重要です。クラウド環境とオンプレミス環境を統合する際には、セキュリティ対策やデータ管理の方針もしっかりと決めておきましょう。
salesforce連携時に注意すべきセキュリティ対策

salesforceデータ連携時には、セキュリティ面でのリスクにも十分注意しなければいけません。特に、外部ツールとのAPI連携では、データのやり取りが増えることで情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。
連携時に注意したいリスク
外部ツールとsalesforceとを連携する際には、外部からの攻撃や内部不正による情報流出のリスクに注意しましょう。
特に、以下のようなリスクに注意が必要です。
データ漏洩:不許可の第三者によるデータ閲覧
認証情報の漏洩:APIキーやアクセストークンが管理されず、不正なアクセスを許してしまう
内部不正:内部者による不適切なデータ操作や持ち出し
こちらのリスクを防ぐためにも、厳格なアクセス管理と暗号化を徹底し、不正アクセスの防止策を講じることが不可欠です。
権限管理とアクセス制御の考え方
salesforce内のデータにアクセスできるユーザーやツールには、必要最小限の権限を付与することが鉄則です。
【具体的な対策例】
アクセスレベルの設定:部署ごとで、業務に応じた適切な権限を割り当てる
IPアドレス制限:特定のIPアドレスからのみアクセスを許可
APIアクセスの制限:不要なAPIアクセスを制限。不審なアクティビティを監視
適切なアクセス管理を行うことで、データの安全性を確保しながら、業務の利便性を維持することができます。
ログ取得や不正アクセス対策など具体的なセキュリティ対策
安全性を高めるには、通信の暗号化や監査ログの取得といった具体的な対策も忘れてはいけません。
【セキュリティ対策の例】
通信の暗号化:API連携時のデータ通信は、SSL/TLSを使用し暗号化
監査ログの取得:salesforceの監査ログを取得し、定期的にチェックする
定期的なパッチ適用と脆弱性管理:パッチの適用を怠ると、既知の脆弱性を突かれて不正アクセスを受ける可能性が高まる。
適切なリスク管理と対策を実施することで、salesforce連携の利便性を維持しつつ、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
連携で効率を上げるなら業務プロセスの見直しと組織体制が重要

salesforceを最大限活用するためには、既存の業務プロセスを見直し、組織全体でデータを活かす仕組みを構築する必要があります。
属人的なプロセスや重複作業を洗い出す
salesforce連携を効果的に活用するには、まず属人的なプロセスや重複作業を洗い出すことが重要です。属人的な業務が多いと、業務が滞るほか、データ管理が曖昧になるリスクが高まります。また、複数のツールやシステムにデータを手作業で入力していると、人的ミスの原因にも繋がりかねません。
【属人的なプロセスの例】
マーケティングと営業部門の両方で、同じ顧客情報を二重入力している
Excelなど汎用ツールでデータ管理が行われ、最新情報の反映に時間がかかる
顧客対応履歴が共有されておらず、重複した対応が発生している
このような課題を解決するためには、情報を一元管理できる環境を整備することが重要です。また、ワークフローを自動化できれば、より戦略的な業務にリソースを集中させることができるでしょう。
データドリブンな意思決定に向けた組織体制も重要
salesforce連携を成功させるためには、データを活用できる組織体制が重要です。部門間で共通のKPIを設定し、同じデータ基準で意思決定を行う仕組みを構築しましょう。
例えば、営業とマーケティング部門で異なる指標を重視していると、方向性がずれ、データの解釈にも違いが出ることがあります。
【迅速な意思決定のための共通KPI】
営業・マーケティング共通のKPI:リード獲得数、商談化率、成約率
カスタマーサポートとの連携KPI:問い合わせ解決率、顧客満足度スコア、継続契約率
また、salesforce連携後の運用を軌道に乗せるには、レビュー会議やガイドラインの見直しも定期的に行いましょう。
まとめ
Salesforceを導入している企業の多くが、顧客情報の分散や運用スキル、人材不足に課題を抱えています。「MAの効果をSalesforceで可視化できていない」「キャンペーンと商談が紐づいていない」「MAとCRMがどのように連携されているか分からない」といった課題もあるでしょう。
toBeマーケティングは、データローダーを含めマーケティングオートメーションであるAccount EngagementとSalesforce CRMにフォーカスした導入・活用支援メニューをご用意しています。
専門のサポートメンバーが導入後の運用における様々な疑問や困りごとに対応していますので、ぜひ検討してみてください。
Salesforce CRMの活用成功事例 6選のご紹介 〜顧客データ統合とDX推進のポイント〜
本資料は、Salesforce CRMを活用した顧客データの統合および業務プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX )に取り組む企業様の成功事例を多数ご紹介しております。
\詳細はこちらをクリック/